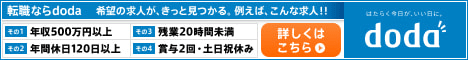皆さまこんにちは
現在私は某東証一部上場企業の営業部門で管理職をやっています。
そのミッションの中で、年に数回、新人・中途の採用担当官も行ってます。
ここでは「この人が欲しい、この人と仕事がしたい、この人なら上手くやって行ける」と思った時の特徴をまとめたいと思います。
採用試験のポイントを知るその前に
さて、その話をする前に前提条件「最低でもここは守ってもらわないと・・・」と思ったことを話します。
現代では人材獲得や企業風土の変化により「服装の自由」がとりだたされ、かなり自由な社風を持った企業が増加してます。
実際私の会社でも社内現場では私服で出社している人もいます。
こういった自由な風土は企業の活気が高まるので、ある程度自由な服装が許されている状況です。
面接の場においても私服の着用が許されているケースも多々あるようです。
しかし、実際に面接を行うのはどんな人なのでしょうか。
一次面接では人事担当など比較的若い世代の人が面接をするケースが多いため、現代の風潮への理解は多く持ってます。
ただ、二次面接以降は現場の管理者が直接実施します。
採用を決定するのは人事担当者ではなく二次面接以降の現場の管理者です。
そこで二次面接官の世代を考えてみて下さい。
ベンチャー企業や比較的早く上場を果たした企業では若い世代の管理者がいると思いますが、大抵の日本の企業はまだまだ年功序列が根付いており、40代以降の人が面接を行います。
そこで必ず見るのはビジネスマナーです。
言葉遣いをはじめ、身だしなみ、面接態度、服装の良しあしを見られます。
私自身も40代後半なので、やはり価値観が現代の若者とは異なります。
少なくとも面接の場はビジネスシーンと捉えているので、やはり服装はスーツと考えてしまいます。
頭では自由な社風を意識していても、感情が拒否反応を示してしまうのです。
もしそんな恰好で面接に来られたらそれだけで正直アウトです。
理由はイメージも確かにありますが「顧客と折衝する場面でそんな恰好をされたら」と不安を抱くことも理由の一つです。
以前、真っ青な上着にややヒラヒラした服を着て面接に来た女性の方がいました。
実際、美人の部類に入る方で相当な自信があったのでしょう。
ただ、少なくともビジネスシーンで着るにはちょっと・・・と思う服装でした。
まあ、自己主張が強い部類の人なんだろうと予想をしましたが予想通りでした。
私と一緒に面接をしたその当時の役員は女性大好きな方で「あー採用されてしまうかも・・・」と少々不安を抱きました。
面接の場は和やかに、というかその役員が和やかになるように誘導していたのですが、女性は得々としてアピールしてました。
その女性は面接が終わる頃には足を組んで、椅子にもたれかかってました。
役員も上機嫌で話をしていたので「あーはいはい、採用ですね?」と面接が終わってタバコ部屋で雑談をしていると「ありゃダメだな」と一言。
見た瞬間に不採用と思ったそうです。
女性好きの役員の発言か?!と正直思いました。
その役員は古いタイプの人間ではありませんが、身だしなみには大変気を遣っている人で、当人的には「公私が区別できないだらしない奴」という印象を持ったそうです。
この女性のようなタイプは、外資系からの転職組にはときどき見られます。
欧米の外資系企業を受けるのであれば、それでも良かったのかもしれませんが、その人の不幸(不幸じゃないかもしれませんが)は日本企業を希望したことでしょうか。
日本の企業では年配の人はそんな価値観を持っている人が多く、社員はそんな人たちに教育をされて育ってゆきます。
外資系の人でも商談の際はバリッとしたスーツ姿です。
※社内現場ではジーパンにTシャツの人も大勢いました。
話しを戻しますが、初対面の面接の場でわざわざ印象を下げる必要はありません。
つまり私服やそれに相当する恰好で面接を受けると、上記のような印象を持たれるリスクが有るということです。
いくら世の中が自由な風潮になりつつあるといっても、採用者側でそんな認識を持っている人が圧倒的多数なのは事実です。
「俺はこれがポリシーなんだ!」「私服OKの職場しか就職してやる気は無い!」などの人以外は上下が揃ったスーツ、面接前にはトイレで髪型を整え、靴をティッシュでふいて身だしなみは最低限整えておきましょう。
それが一般的な日本のビジネスマナーで、知らない人はほとんどいないと思いますが何度か見たことがあるので、念のため記載します。
採用担当者が「この人は採用!」と即決した3つのパターン
さて、本題に入りたいと思います。
私自身も年に何度も採用試験の面接官を担当しております。
自慢ではありませんが、人気企業なので希望者は募集広告を出すと殺到します。
そんな狭き門でも採用試験を潜り抜けた人、面接官がこの人が欲しいと思い採用に至ったパターンを3つ紹介します。
【ポイントその1】自分のアピールと相手の理解をバランスよく行う人
ときどき面接時にこれでもかって言うほど自分中心の価値観をアピールしてくる人がいます。
その人が抜群の説得力を持っている人なら、ほぼ一方通行の面接をしても採用になるケースもあります。
しかし、アピールが得意な人は、割と高い確率で人の話を聞くことが苦手な人だったりします。
こちらの話を聞いているのにも関わらず、見当違いな回答をするだけではなく、その話を延々と続けます。
例えば、「前職で困ったことは何か、そしてそれをどのように解決したか」を聞いたときのことです。
その人は「職場内での人間関係について」話しを始めました。
「きっと職場内でのコミュニケーションがうまくいってなかったので、それを改善した話しなのだろう」と思って聞いていると、自分の言うことを聞かない上司や後輩の欠点を指摘しだしました。
悪口というよりは「こんな人がいた」という話し方でしたが、その後どうしたのかを聞くと、「自分が我慢をしており、相手のわがままを聞いていた」とのこと。
要は「俺は我慢強い人間だ」ということを言いたかったのでしょうか。
そして、自分のノウハウがいかに優れているか、知識が有るかをアピールし、話しが逸脱したまま時間が過ぎてゆきました。
優しい見方をすれば、面接の緊張が有ったのかもしれませんが、もちろん採用しようとは思いません。
少々極端な例ですが、話しが自分中心になってしまうことが意外に多く見受けられます。
私の聞き方にも問題があったのかもしれませんが、上記での一番の問題点は「相手が求めている回答をしなかった」こと、「それに気づき軌道修正を行わなかったこと」です。
大抵の場合、面接をする際、面接官は相手中心に会話を進めます。
少なくとも採用される人たちは、相手の求めている回答に対して軌道修正を怠りません。
この回答でよろしかったですか?
ご質問の主旨はこのような意味ですか?
このような一言で面接でのコミュニケーションがスムーズになります。
さらにデキる人は質問を受けた段階で、「こんなことを話そうと思います」と言って面接官の反応を見てます。
「ん?」という反応なら、その場で軌道修正し、「うんうん」という反応を見てから話を始めます。
この一言が有るか無いかが運命の分かれ目になります。
もし、自己アピールが苦手だったとしても、相手の求めている回答を確認する作業を怠らない人は「一方的に押し付けるタイプではない、コミュニケーションができる人だ」と判断し、それだけでも好印象を持ちます。
普段の何気ない会話でも練習になるので、是非実践してみてください。
【ポイントその2】自分なりの回答を持っている人
自己アピールが得意な人、苦手な人がいると思います。
これは得意な人が断然有利かというと実はそうでもありません。
もちろん自己アピールが得意な人はそれだけでもポイントにはなります。
例えて言うならレストランのショーウィンドウでのステーキやお寿司は見た目でたっぷりアピールされます。
これに対し、自己アピールが苦手と言わないまでも、「恥ずかしい、上手くしゃべれるか不安」という人もいると思いますが、そんな人たちに対して、面接官はできるだけその人の内面を知ろうとします。
面接官の立場になって考えてみて下さい。
せっかく会社が人材獲得のためにお金を出して集まった人材は、できるだけしっかり話しを聞いておこうとします。
私の経験上の話しですが、自己アピールが得意な人より、そうでない人の方が観察眼に優れているケースが意外と見受けられます。
会社からあるミッションをクリアするために、その市場について詳しい人が必要という経緯で募集を行ったときのことです。
数人の応募がありました。
ほぼ営業経験者なので、皆それぞれ自己アピールは得意な人たちでした。
ただ、そんな中でも営業経験があまりなく、久しぶりに営業をしたいという希望者がいました。
その人は営業経験よりも社内での現場経験が長く、ときどき営業に同行し顧客と会うことも有るといった方でした。
まずなぜ営業を希望したかを確認すると「現場でつちかったスキルを営業として展開したい、売上という分かりやすいステータスが欲しい、自分の現場でつかんだ理論を営業として試してみたい」とのことでした。
面接時に出た会話の中でこんなことを言ってました。
「営業から聞いた話を実はこうではないか?とお客さんに聞いてみると実態はその通りでした」とのこと。
技術者上がりの営業によく見うけられる特徴ですが、正にそのタイプです。
このような人たちの特徴として、通常の営業では到底持ちえない説得力をもたらすことが多々あります。
面接ではアピールもあまり上手ではなく、むしろ現場としての我が強かったり、ビジネスマナー的に大丈夫か?と思われるところも見て取れたのですが、「営業をやりたい」とヤル気を持っていたので、この人を採用することにしました。
結局、その人は数年で年間数億という売上を達成することができました。
入社後にその人が優れていた点を挙げると、現場と顧客とのやりとりが実にスムーズで、営業が余計なことをやっている間に、さっさと手配を済ませている、といった効率化を見事に果たしていました。
さて、話しを元に戻しますがアピールはむしろ下手だったにも関わらず「この人を採用したい」と思った点は「内容の深み」です。
営業経験豊かな人を「ステーキ」だとすると、この人は噛めばかむほど味が出てくる「アワビの干物」といったところでしょうか。
面接の短い時間の中で、対象者のことを深く知ろうとしても限界があるため、面接官も決断をしなければなりません。
その一瞬の中ででも「対象となる市場での課題、課題に対する回答」をその人なりに持っていることが分かりました。
それはある意味、採用前は仮説でしかないのですが、よく面接時に「入社後はこんなことをやりたい」というアピールをするシーンがあります。
実はここで採用と不採用が分かれる瀬戸際になっていることが多々あります。
ここまで言えばもうお分かりでしょうが、自分なりの仮説と回答を持っている人を面接官は重用します。
その意見が的を得ており、より高い次元で装備されていれば文句は無いのですが、仮に的を得ていなくても深く考えて行動する人だという印象を持ちます。
採用試験を受ける前にその会社で何をすれば実績が出せるのか?ということをよく考えて、それを面接官にぶつけてみて下さい。
【ポイントその3】会社全体バランスの利益につながると感じた人
少々抽象的ですが、面接官をしている人は部下数人から数百人を抱える管理者が多く、個人の利益よりも会社全体の利益を常に考えて行動している人が圧倒的多数を占めています。
そんな人たちの琴線に響くことが二つあります。
その人の部下としてこんな貢献ができる、会社全体の利益としてこんな面で役に立てるということです。
何故かというと「自分の組織は他の組織よりも優秀でありたい」という思いと、「会社から命令されている会社全体に関わる利益の追求を求めなければならない」という思いが有るからです。
よく「経営視点に立った考え方」という言い方を耳にしますが、これは「経営的視点を身に付けろ」と言っている訳ではなく、極端に言うと「俺たちの立場を分かってくれよ」と言っているのです。
といっても「太鼓持ちになれ」という訳ではありません。
「経営層や管理者達が何を求めていて、何をすれば会社の売上に貢献できるか、ということを考えてアピールすることが大事だ」ということを言ってます。
もっと分かりやすく言うとこんな子分が俺の下にいてくれたらなあと思わせることです。
それではどんな場合に経営層や管理者はそんな風に思ってくれるのでしょうか。
例えば、前述の「自分なりの回答を持っている人」の中では、会社が持っていないスキルを持った人が来てくれたら「自分の部署の底上げができる、会社の方針にも合致している」と考えたために採用されました。
また、そのようなスキルを持っていなかったとしても、会社を外から見た場合「この製品をこんな市場へ展開すれば面白い」だとか「自分が経験したこんなスキルを役に立てたい」といった話しをすることができると思います。
それをもう少し推し進めて、会社全体のどんな部分に自分が貢献できるかを考えてみて下さい。
「自分の持っているスキルを役立てたい」という思いも、自分ひとりの中で囲っていては片手落ちです。
それを「組織としてこんなノウハウを確立したい」という思いを加え、それがより具体的になると、より経営層や管理者の琴線に響くアピールができます。
以前こんな面接者がいました。
どちらかというと自分のアピールよりも質問を多くしてました。
一通りの経歴を話し終えた後のことです。
「私は貴社に入社後には今お話ししたようなことに貢献できると思っておりますが、〇〇さんはどんな組織を作りたい、またはどんな営業展開をしたいと考えておりますか?」
それに対し私は「こんな市場に対しこんな営業展開を考えている、会社の方針としてはこんな方向性を打ち出している」と回答しました。
「それではこの活動をする際に、こんな要素を取り入れるとより営業活動が効率的になると思います。微力ながらこの部分で私はお役に立てると思います」
その後は面接というよりも、上記のような会話が進み、営業展開の打ち合わせのようになりました。
私を初め私の上司達も「この人を逃すな」と採用を即決しました。
話しを元に戻しますが、採用側が何を求めているかを聞き出し、自分なりの仮説を加えることで、より採用の確率が高まります。
採用を判断するのは人事部門ではなく、現場の管理者達です。
その管理者が求めていることは自分のポジションを固め、より上に昇ることです。
そういった管理者の要求は、自部門の成果・会社への貢献なので、全体バランスを考えたアピールをすることによってより採用の確率を上げることができます。
採用試験の準備として、自分が持っているノウハウをいかにその親分の為に役に立てられるか、全体バランスを考えた発言になっているかを考えてから臨んで下さい。
採用担当の琴線に響くスキルを身に付ける
さて、上記で述べた採用側の琴線に響くトークを簡単に思いつく人もいれば、なかなかそんなネタが思い浮かばない人も多くいると思います。
そこで、自分のアピールポイントとキャッチボールの練習、または自分では気付いていないネタ作りには第三者に意見を聞くことが大変有効です。
そのためには、友人に見てもらって指摘してもらうという方法もありますし、皆さんも良くご存じの、転職エージェントを活用する方法があります。
私が今回述べたポイントは以下になります。
・面接官との会話のキャッチボール
・自分なりの仮説と回答を持つこと
・経営層、管理者が気している全体バランスを考慮
ただ漠然と転職エージェントを利用してもあまり効果を発揮しないので、先ほど私が述べた内容を想定したり、自分なりの要素を加えながらエージェントに実地さながらの訓練を依頼したり、どんなアピールポイントが有るかを聞いてみると、より効果的な手段やポイントを教えてくれます。
今、転職エージェントの活用は当たり前になっているので、その中でもどのエージェントが良く、どのように活用すれば良いかを以下に述べたいと思います。
まず@typeです。
この転職支援サービスは何が優れているかというと、自分のスキルを登録しておくと転職の可能性がある企業をどんどんメールで紹介してくれます。
メールの内容はスカウトもあれば、オファーと言ってスカウトの一歩手前の案内を@typeを通して教えてくれます。
さらに「スキルマッチング、パーソナリティマッチング、応募歓迎」などのお知らせをメール通知してくれます。
特に「スキルマッチング」は登録した自分のオリジナルスキルシートとのマッチ度をシステムが自動算出し、経験業務の募集記事を紹介してくれるので非常に便利です。
マッチング機能は自分が知らなかった可能性を気づかせてくれる時もあるので、異業種へ転職したいのであれば直ぐに可能性がある企業が見つかります。
また、ここが今後の転職先を選ぶのに大変重要になるのですが、今の自分の適正年収を調べることができます。
システムがスキルシートを読み込んで、その場で適正年収を教えてくれます。
自分の適性年収を知ることによって、どのレベルの企業に行ける可能性があるのか、また、どの程度自分を高く売り込むことがでるのか、さらにスキルアップにはどんな企業に可能性があるか、どんな適性があるのかを知ることができます。
次にDODAです。
DODAの優れている点はサイトで検索できる企業以外の企業がどの転職サイトよりも豊富なことです。
その企業群はDODAとのグリップが非常に強いため、いつでも紹介できる企業のラインナップがそろってます。
DODAのシステム上で企業検索することもできますが、一番良い方法はDODAの最も得意とする、転職エージェントに会って自分が希望する条件の企業を紹介してもらうことです。
普通にハローワークなどで転職活動をすると全て自分でことを進めなければならないところを、職務履歴書のよりよい書き方から、最終面接、採用までをエージェントがサポートしてくれます。
私が転職をする際は、複数の転職エージェントを利用しましたが、サポートの質が非常に高く、他の転職エージェントと比べても群を抜いてました。
一番良かったのは、採用試験中の企業とネゴを進めてくれることです。
そのため、採用試験中の企業の採用率は高まるし、企業との交渉事もやってくれるので、手間をかけずに効率的に転職活動ができます。
また、以下は有名どころと特化した転職サイトのリンクを集めてみたのでよろしければ参考にして下さい。